JANSI新卒職員インタビュー

*ピアレビュー計画部
運営グループ
T.Kさん
応用理工学専攻
2017年度 JANSI入社
2018~2020年度 北海道電力(株)泊発電所出向
2021~2022年度 JANSIピアレビュー計画部勤務
2023年度~ JANSI技術支援部 運転グループ勤務
*2023年2月現在
―WANOというとチェルノブイリ原子力発電所事故を契機に世界の原子力発電事業者が、相互の切磋琢磨と交流により原子力発電所の運転の安全性と信頼性を高めることを目的に1989年に設立された国際組織ですね。連絡窓口とは具体的にはどのような業務を行っていますか?
一つはお互いのピアレビューのスケジュールのすり合わせや確認です。ピアレビューは事前に発電所の情報を受け取り入念に準備したうえで2.5週間現地に滞在する長期プロジェクトです。そのため、発電所や当該電力会社に過度な負担とならないよう、調整が必要となってきます。また、WANO側からJANSIレビュワーの派遣を求められたり、逆にJANSIから海外レビュワーの派遣をお願いしたりもします。WANOのレビューにJANSIレビュワーの参加を依頼することもあります。そういった相互の連携が主な業務です。
―相互的な協力関係にあるのですね。翻訳関係の業務を具体的に教えてください。
レビュワーが現場を観察した結果をまとめたレポートや発電所からお預かりした規則等の文書等ピアレビュー関連の文書の翻訳作業となります。以前はほぼ全ての文章を翻訳会社へ依頼していたのですが、近年はAI翻訳を導入し、社内で翻訳作業を行うようになってきています。システムにピアレビュー特有の単語や表現を登録し精度を上げ、伝わりやすい表現に工夫しWANOから派遣された海外レビュワーとのコミュニケーションが円滑に行えるように心がけています。
―現在の業務についてよくわかりました。JANSIは国内の原子力発電所の安全性向上にフォーカスした組織ですが、国際的な組織との連携も大切にして、協力し合い、切磋琢磨しているのですね。
―就活についてお伺いします。JANSIに入ろうと思った理由は何でしょうか?
大学では電子工学を学んでいたので、国内の電力関係の仕事に関わりたいと思いJANSIにしました。関係する企業を就活サイトで探していたところ、JANSIに行きつきました。
―JANSIにした決め手は何だったのでしょうか?
父が福島事故の時に現場で対応をしており、原子力発電所に安全性向上に関心がありました。また、特定の発電所だけでなく、日本全国の発電所に携わることが出来る点が決め手になりました。

―では入社後の年度ごとの仕事について教えてください。
1年目はJANSI内の各部で社内研修に参加しました。年度の終わりに島根原子力発電所のピアレビューに同行しました。その他にはメーカーピアレビューにも同行しましたね。レビュワーの業務も少しだけ体験しました。
2年目から4年目は泊発電所に出向し、発電所員の1年目の方々と同じように教育を受けました。2年目はまず、集合研修で発電所の概要などを3か月ほど勉強しました。その後運転員見習いとして年度末まで現場に同行しました。泊発電所は3交代制での勤務でしたね。
3年目は現場運転員として勤務しました。業務はチームで協力して行います。仕事上の連携はチーム内がほとんどですが、前年に一緒に教育を受けた発電所の新人の方々とは同期のような一体感を持つことができました。気軽に相談ができ、遊び行ったりしました。現在もその関係は続いています。
4年目は発電室のデスクワークで、保修部門と運転部門の間に入り作業を調整する業務に携わりました。発電所運転員を3年間担当するより有益なのではないかという泊発電所の意向で前年までとは大きく異なる業務に従事させていただきましたね。4年目は運転員時と異なり通常の勤務体制でした。
5年目以降はJANSIに戻り、先ほどお話したピアレビューの調整業務をしています。昨年は高浜、美浜両発電所のピアレビューに同行しました。さらに、今年は泊発電所のピアレビューにレビュワーの研修生として参加しました。
―いよいよJANSIの主な業務であるレビュワーとしての教育が始まったのですね。
そうですね。現状はまだレビュー活動の練習といった位置づけですが、来年からは自身の担当する専門分野の方向性が決まり、レビュワーになるための本格的な育成と業務が始まります。
―着実なキャリアフローを経ていらっしゃいますね。
―出向中のお話に戻りますが、北海道での生活はいかがでしたか?
北海道にいた頃は発電所の仲間と遠出することも多かったです。運転員はタイミングが合えば連休も取りやすいので。スケジュールを合わせて連休を取り、海外旅行に出かけたりしました。しっかりとプライベートの時間も確保できます。
―オフも楽しんでいらっしゃったのですね。出向先とJANSIの雰囲気の違い、印象に残っていることはありますか?
何といっても年齢層が全然違いますね(笑)。発電所は新人だけで30名ほどいました。集合教育は皆で授業を聞いているので学校のクラスのような感じでした。JANSIの新卒採用は毎年1名~4名ほどですが、私が入社した年は私一人のみでした。ただ、JANSIで同期がいなかったことで困ったことなどはほとんどありませんでしたね。父親世代の職員からは、エキスパートとしての高度な専門的知識や技術を教えてもらえますし、20代30代の比較的若い出向者や中途採用の方もいて、話しやすい職場環境です。
―では、JANSIで仕事をしていてやりがいや面白みを感じたことは何でしょうか?
先述の通り今年の秋に泊発電所ピアレビューにレビュワーの研修生として参加したのですが、発電所の方とJANSIレビュワーとの議論を聞いているときに面白いと感じました。運転員として働いた経験もあるため発電所の気持ちもわかるし、そこをくみ取りながら議論を交わす様子から多くの学びを得ましたね。
―3年間の出向の経験が活きているわけですね。
やはり実際に発電所に行ってみないと発電所側の立場や苦労、考え方は実感できません。それを理解しているからこそピア(仲間)として意見が交わせると思います。
―JANSIは発電所に対して「指摘する側」のような立場に思われがちですが、そういった観点で見て発電所のリアクションはいかがでしたか?

発電所は提示した改善事項に対して、具体的にどう対応したらいいかを知りたがっていました。その気持ちはよくわかりますが、JANSIの活動の柱はあくまでも「評価・提言・支援」です。家庭教師役として、改善点を見つけ、提示し、強化するためのアドバイスを行い、個々の環境に合った具体的施策を自ら考えて実施してもらう、そういった観点で向き合います。支援活動も具体的な施策を提言するものではなく、電力会社間の意見交換の場を提供したり、国内外の最新知見を共有したりといった活動になります。
―若手目線で見たJANSIの「今後の課題」はありますか?
JANSIで採用された新卒職員の中にレビュワーのリーダーになった人はまだいません。これは新卒採用を始めてからまだ7年しか経っておらず、私たちがレビュワーとしての力量を習得する為の教育プロセスの過程にいるからです。私はJANSIの新卒採用が始まって2年目に入社しており、採用計画の中でも草創期に位置しています。先んじて教育プロセスを経ていますので、自身の感じたことや改善すべきと考えた点などのフィードバックを行い、後輩や今後入社される方の為にも、より良い教育プロセスとなるよう改善に努めたいと思います。
―ベテランの方々が多い組織ではありますが、若手が活躍できる場はたくさんありそうですね。
―今後の目標がございましたらお聞かせください。
まずはレビュワーとしての知識と経験を積んでいきたいですね。それと語学力を磨きたいです。WANOの窓口をやっていると、レビュワーを派遣してくれないかという要請がよく来ます。海外の発電所のピアレビューへ行くことになるので、当然現地での会話は外国語(主に英語)になります。レビュワーとしての知識・経験、そして語学力を身につけることで、窓口だけでなく自身が派遣されるレビュワーになれればと思っています。また協会全体としてもその要請に対応できる人が今以上に増えればいいなと思います。
―最後に就活生にメッセージをお願いします。
しっかり悩んで、悔いのない決断をしてください。その中でJANSIも一つの候補になると嬉しいと思います。
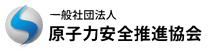
―まず、運営グループでの現在の業務について教えてください。
原子力発電所へ赴き安全性向上のために評価・提言を行うピアレビュー業務に関する調整や資料の翻訳、WANO(世界原子力発電事業者協会)との連絡窓口、運転分野のレビュワー研修生としての参加、ピアレビューのセルフアセスメントなどを行っています。