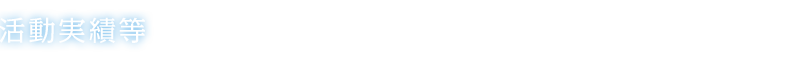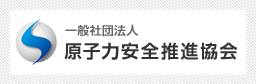- HOME>
- 活動状況 >
- PRA用パラメータ専門家会議実績 >
- 第7回議事概要
PRA用パラメータ専門家会議 第7回議事概要
| 日時 | 平成26年9月25日(水)13時30分 ~ 15時55分 |
|---|---|
| 場所 | 原子力安全推進協会 13階 第1,2会議室 |
出席者(順不同 敬称略)
| 委員 | 笠井主査(秋田県立大学)、栗坂委員(JAEA)、吉田委員、桐本委員(電中研)、 松中委員(東京)、友澤委員(四国)、藤井委員(東芝)、曽根田委員(日立GE)、 黒岩委員(三菱)、佐藤委員(TEPSYS)、倉本委員(NEL) |
|---|---|
| 常時参加者 | 西野(JAEA)、曽我(電中研)、鳴戸(NESI)、門田(NEL)、根岸(GIS)、 玉内(日本原燃) |
| 事務局 | 橋本幹事、河井、鎌田、錦見(JANSI) |
議事概要
- 前回議事録の確認
- 起因事象発生頻度推定手法の検討
委員より、起因事象発生頻度推定手法の検討について説明した。概要及び主な質疑応答、コメントは以下のとおり。- 計算コードをBUGSからStanに変更し、米国評価値を事前分布として階層ベイズ手法を適用し、PWRおよびBWRのLOCAのデータについて試算した。
- PWRのLOCAに関するBUGS計算による従来試算では、自己相関、一般発生頻度の収束性の問題および超母数σの分布幅不足が見られた。
- 米国評価値を事前分布としたStan計算では、一般発生率は収束していないがハイパーパラメータは収束した。また、自己相関および超母数分布幅不足の問題は解決し、計算結果もほぼ同等であった。なお、マージによって一般発生率の収束性は改善できる。
- BWRのLOOPに関するBUGS計算による従来試算では、超母数事後分布幅の不足が見られるため、米国評価値等を利用した事前分布を用いる等の改善の余地がある。
- 事象発生数のあるプラントとないプラントで発生頻度の差が出ており、階層ベイズの結果としては適切な傾向が出ている。
- 階層ベイズによる類度推定のまとめとして、自己相関についてはthinningまたはStanの利用により低減できる。また、一般発生頻度の収束性が悪い場合は、個別発生頻度が収束していればそのマージにより一般発生頻度を求めることができる。結果の妥当性チェックとして、発生頻度予測分布を求め、実績データとの整合性を確認するのがよい。
- 機器故障率の試計算について
常時参加者より、機器故障率の試評価について説明した。概要及び主な質疑応答、コメントは以下のとおり。- 本専門家会議で検討している手法(以下、新手法)の適用性を検討するために26ヶ年データの試計算を行った。
- 旧手法からの主な変更点は、①サンプリング手法の変更、②一般機器故障率の導出過程の変更、③ハイパー事前分布の変更である。
- 実績データの規模(故障実績、運転時間、デマンド回数)が異なる故障モードを対象に新手法の感度解析を行った。
- 新手法(EPRI手法、加重マージ)による一般機器故障率の導出過程において、収束性に問題がないこと、平均値が旧手法と同程度になることを確認した。ただし、従来手法では、サンプリングの外れ値の影響により新手法と比べて平均値が、一桁大きくなる場合があった。
- 事前情報による影響を確認した結果、収束性に問題が見られるケースおよび計算が流れず解が得られないケースがあった。また、国内故障実績が多い故障モードについては、異なる事前情報を与えても平均値およびEFは同程度になり、実績がない故障モードについては、事前情報の影響を強く受ける結果となった。
- 旧手法による26ヶ年で一般機器故障率の差異が大きい故障モードを対象に、新手法による26ヶ年データの再評価を行った。また、プラント固有故障率についても比較を行った。その結果、プラント固有故障率の一部に収束性に問題が見られるケースがあり、新手法の一般機器故障率の平均値およびEFは、導出方法の変更と事前情報による影響によって、共にほとんどの故障モードで小さくなった。
- 新手法の適用性を検討した結果、収束性に問題が見られるケースについて外れ値の影響を取り除く等の改善が必要であることおよび実績の少ない故障モードについては適切な事前分布の設定が必須と考えられることを確認した。
- 今後のスケジュール
事務局より、今後のスケジュール、次回議題案について説明し、第8回PRA用パラメータ専門家会議を10月30日(木)に開催することとした。
以上