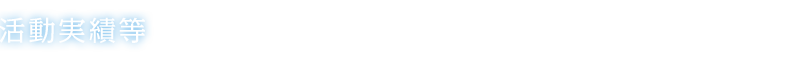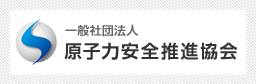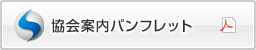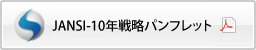日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所にて
第200回安全キャラバンを実施
2025(令和7)年9月30日、茨城県東海村にある日本原子力研究開発機構 原子力科学研究所 先端基礎大会議室において、JANSIの安全キャラバン(安全講演会)を行いました。なお、講演会には他事業所からWebによる参加もありました。
1.安全講演会
原子力科学研究所では大会議室に51名、Webから226名が参加をされ、終始熱心に聴講されました。

講演に先立ち、日本原子力研究開発機構 安全・核セキュリティ統括本部 安全管理部長 齋藤 圭 様から、「これまでに安核本部では事故・トラブル防止のために、拠点長との意見交換、役員による現場パトロールなどを通してトラブルゼロを目指す活動に取り組んでいる。
今回はJANSIの安全講演会を通して、安全最優先とは何か、また、どのような組織を目指しどう進めていくのかといったところから、更なる気づきや課題認識が深まることを期待している。」とのご挨拶をいだだきました。
講演では、原子力安全推進協会 安全基盤部 安全文化Gグループリーダーの深野琢也より,「学習する組織と安全」と題して、
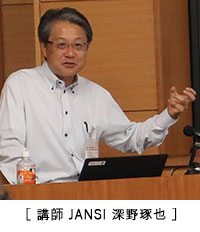
- 安全の仕組みと組織文化
- 安全向上と組織学習の関係
- 組織文化の把握と改善
- 事例の紹介
など、安全文化にまつわるアセスメントのアプローチと事例の紹介を通して、安全文化の目的や本質を普段の仕事や職場に即してイメージしていただけるように講演を行いました。
講演の要旨は以下の通りです。
- 複雑にもつれ合う現実世界では、些細な不確実性(揺らぎ)も予期せぬ重大な事故につながることがある。揺らぎを全て排除するのは無理であるため、組織が大きな過ちを防ぐには、危険な揺らぎを早期に察知し、レジリエンス(本来の姿に戻す復元力)を働かせることが肝心である。
- そのためには、情報を広く速やかに共有し、集合体としての認識・予測・対応(学習)能力を高める必要がある。しかし、実際にはしばしば組織自身のありよう(組織文化・体質あるいはマインド)が、誰も意識できない形で人々の発想や選択を方向付け、視野を限定してしまう。つまり、人を大切にし、信頼と敬意で結ばれた開かれた組織でないと、組織の学習能力は歪み、ひいてはレジリエンスが働かないおそれがある。
- 安全文化とは特別な何かではなく、組織の本来あるべき健全なありように他ならない。自らのありようを正しく認識することが前提であり、批判的・客観的な視点からの組織文化アセスメントは、貴重な学びの機会である。
- 上述したことは、御社の掲げるビジョンの実現に向け、戦略を策定し実践・組織学習を行うことについても同様である。すなわち、組織(文化)のありようをシステミックに把握し、必要な変革を通じて健全な組織(文化)を醸成し続けることが重要である。組織のリーダーは組織文化の形成に決定的な影響力を及ぼす立場にあるため、こうしたことを率先して理解し、体現し、主導することが望まれる。
講演会終了後のアンケートでは、
- 組織文化の理解と改善を通じて、安全性の維持・向上に資するリスク低減活動の実効性を高める内容であり、非常に有益であった。
- 管理職に期待される役割について、事例紹介を交えつつ解説され、理解しやすい内容であった。
- 安全文化と組織学習の重要性を再認識するとともに、安全に向けた継続的な改善の必要性を強く感じた講演であった。
- どのような場合も、大きな事故の根底には、その問題を引き起こした組織的な欠陥があり、経営層と現場の繋がりの重要性を学ぶことができた。
- 日本的安全と国際規格の安全の違いについて理解することができた。
- 現状の組織文化の特性を理解しつつ、関係者との共有及びリーダーシップを図りながら、課題改善に努めたい。
などの意見や感想が寄せられました。
以上