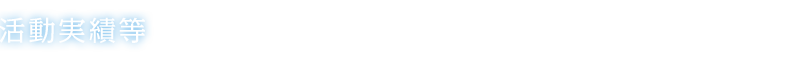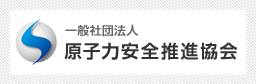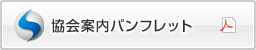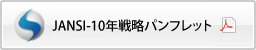原燃輸送株式会社にて
第198回安全キャラバンを実施
2024年12月10日(火)、原燃輸送株式会社本社(港区芝)において、第198回安全キャラバンを行いました。
1.安全講演会
原燃輸送株式会社では、社長を含めた全社員を対象に原子力安全文化醸成活動の一環として原子力安全文化講話を毎年度実施しています。今年度は、JANSIの安全キャラバンを原子力安全文化講話の位置づけで実施しました。
講演では、原子力安全推進協会 安全基盤部 安全文化グループの深野グループリーダーから、「安全に寄与する組織文化アセスメントの考え方と視点~トラブルの再発防止・未然防止のヒント~」と題して、安全文化にまつわる事例の紹介とアセスメントのアプローチを通して、安全文化の目的や本質を普段の仕事や職場に即してイメージし、改善のきっかけとして頂けるように講演を行いました。
講演の要旨は以下のとおりです。
- 組織内部に潜む欠陥や些細な不確実性(=揺らぎ)は、予期しない重大な事故や不祥事につながることがある。揺らぎを全て排除するのは無理なので、組織が大きな過ちを防ぐには、危険な揺らぎを早いうちに察知してレジリエンス(= 本来の姿に戻す復元力)を働かせることが肝心となる。
- それには情報を広く速やかに共有し、組織やその集合体としての認識・予測・対応(= 組織の学習)能力を高める必要がある。しかし、実際にはしばしば組織自身のありよう(= 組織文化・体質或いはマインド)が誰も意識できない形で人々の発想や選択を方向付け、視野を限定してしまい、そのことで安全を阻害することがある。つまり、人を大切にしつつ、信頼と敬意で結ばれた開かれた組織でないと組織の学習能力は歪み、ひいてはレジリエンスが働かないおそれがある。
- 安全文化とは特別な何かではなく、組織の本来あるべき健全なありように他ならない。自らのありようを俯瞰しつつ批判的・客観的な視点からの組織文化アセスメントは、組織の学習能力を高めるための貴重な学びの機会となる。
- 組織内あるいは顧客と協力会社をつなぐ中核としてのリーダーは、組織文化の形成に決定的な影響力を及ぼす立場にあるので、こうしたことを率先して理解・体現・主導するためのリーダーシップを発揮することが望まれる。
講演終了後のアンケートでは、
- 問題の把握や解決のためのアプローチについて、これまで正しいと思っていたことが誤った例であった等、認識を改める良いきっかけとなった。
- リーダーの重要性も再認識しました。リーダーシップ論も学びたいと思います。
- すぐにでも自分の業務において実践できることを多く学べました。定期的に本講演の内容を振り返り、改善を図れたらいいと思う。
- 組織とはどうあるべきか、組織を健全な状態にすることの重要性をあらためて認識できました。
- 「安全」を、つい広辞苑に記載のある意味でとらえてしまいがちだが、「安全」はリスクの存在を前提にして、リスク低減活動を行うことだ、ということを念頭に置いて業務に取り組もうと思う。

以上