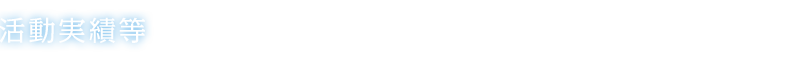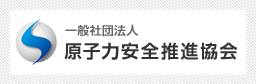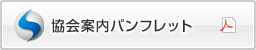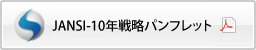北海道電力株式会社 泊発電所にて
第197回安全キャラバンを実施
2024(令和6)年10月15日、北海道電力株式会社 泊発電所において、第197回安全キャラバン(安全講演会)をおこないました。
1.安全講演会
この講演会には、泊発電所をはじめ、北海道電力(株)本店などから128名(内47名がWebによる参加)が出席され、終始熱心に聴講頂きました。
講演では、原子力安全推進協会 安全基盤部 安全文化G グループリーダー 深野琢也より、「「なぜ、ものが言えなくなるのか」を考える」と題して、組織のパフォーマンスを向上させるために重要な「ものが言える環境」について、その重要性や失敗事例、「ものが言える環境」を構築するためにはどこから手を付ければよいか、などについて、理解を深めていただけるように講演を行いました。
講演開始にあたり、泊発電所長 西條様より、
「泊発電所は設工認というステージに移行し、ますます忙しい状況になる中、足元で起きている落とし穴に気付けることが非常に大きな課題である。そのためには一人一人の意見を吸い上げることが非常に大きなテーマであり、本日の講演の内容を是非参考にさせていただきたい」とのご挨拶がありました。
講演の骨子は以下の通りです。
- 「自職場は風通しがよい」との認識は、あくまでも「言ってもよいこと」「異論を言ってもよい範囲で言っている」面もあるのではないか。組織にとっての最大の脅威は、「ものが言えない」ことを意識せぬまま「ものが言えていない」ことではないか。
- 耳を傾けるべき立場にいる上層部の人々は、自分の存在が下位層の人々を押し黙らせる組織の特徴に気づけない。上司が威圧的な態度を取っているつもりがなくても、沈黙の引力は働くことがある。発言することのリスクが大きいと感じた人は、発言するよりも沈黙することを選んでしまうもの。
- ものが言えない、言っても聞いてくれないことが起因となった組織事故の例として、スペースシャトルコロンビア号の事故を紹介。この例の内、打ち上げ時に生じた損傷を確認し検証する機会は何度もあったが、トップのふるまいで、確認ができないという全体の‘空気’ が出来上ってしまい、事故を防ぐチャンスを逃していたことを紹介。
- 様々な考えや多様な人たちの考えを受け入れると、今までの仕事のやり方の良し悪し、問題点などが明確になり、より改善の機会を得ることになるのではないか。そうすることで、複雑で不確実な時代でも、よりしなやかで早く動けるような自律した組織を目指せるようになるのではないか。
- 自己アセスメントで得られた自らや組織のありようを把握し、トップを始め全ての所員が何をすべきか主体的に考え実践するプロセスを経て、「ものが言える環境」が育まれる。
- <主な内容> 1.なぜ「ものが言えなくなる」のか
2.組織事故の事例
3.「ものが言える」環境を育む必要性
4.どうしたら「ものが言える」ようになるのか
講演会終了後の質疑応答やアンケートでは、
●マンネリ化、流される風潮を変えるきっかけになった。
●安全に関することだけではなく、日頃の業務にも必要な内容であり、大変勉強になった。
●組織を改善するためには時間も労力もかかるが、手探りでも一歩踏み出して行動する必要があると感じた。
などのご意見・ご感想を本店の各部長をはじめ様々な聴講者からいただきました。

以上