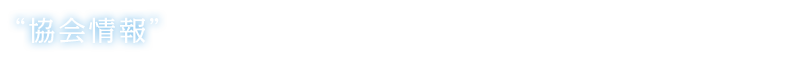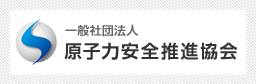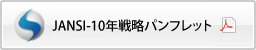電気新聞「時評」 大事故に学び直す
平成26年2月20日
原子力安全推進協会代表
松浦 祥次郎
あの大事故から3年になる。原子力安全問題に多少とも関わった者にとっては、あの事故から突き付けられた課題と向き合いながら考え続ける3年であった。専門家集団である日本原子力学会では、「福島事故が次世代に伝えるものは何か」との視点から会員諸氏の見解を集め、直近会誌3月号に特集記事を公刊の予定と聞く。
本稿では、必須ながら特段に対応が困難と思われる気懸かりな2つの課題を取り上げてみたい。
一つは、安全性評価の課題である。「現在の軽水発電炉技術は福島事故を防止できるか」との設問に対しては、「現在の科学技術的知見に基づいて適切な設備的対応が十分になされて、かつそれらを操作運用する技術が過酷事故対応についても十分に訓練されておれば防止できる」との見解が多くの内外専門家から示されている。
しかしながら同時に「発生確率は極めて低いが、発生した場合の影響が非常に大きい事象に関しては今後あらためて深い研究が不可欠である」との指摘が米国機械学会の福島原発事故報告書「原子力安全の再構築」をはじめ、いくつかの専門家グループの見解で示されており、これも原子力安全専門家の共通認識と考えられる。
この指摘に応じる研究の必要は内外で共通に認識されながらも、具体的な研究手法も実施計画も未だ提案されていない。その理由は、この研究が対象とする事象の範囲を自然現象においても、テロリズムを含む人的事象においても、現在の科学技術的知見と手段を基盤とするのみでは適切に予測することができないとの事情にあると考えられる。
現実的に可能な選択は、科学技術的知見に基づく予測可能なリスクに対しては実行可能な限りの対策を実施し、それを超えるリスクは残余のリスクとして、他のリスクと比較衡量し、それが社会に受け入れられるかどうかを判断するということではないであろうか。
この選択を理性的に実施できるようになるには、社会一般のリスクリテラシーがある程度以上のレベルに達している必要がある。このような選択が可能となるための社会改革に関する戦略的研究が試みられることを強く期待したい。
もう一つの課題は低線量放射線被ばくの人体影響に関する総合的かつ微視的研究である。
福島事故から3年を経過した今も約15万人の避難者の多くが自宅に帰還ができていない。その大きな原因が、低線量被ばくの人体影響に対する理解が、避難者個人、行政、社会一般に十分理解され納得されていないところにあるようにみえる。
低線量影響に関しては、既に膨大な疫学的研究によって、放射線作業における放射線障害防止には必要十分な知見が得られており、その知見に基づいて放射線作業上の管理が適切に実施されている。
しかし、今回の事故後の社会的状況は、科学的、且つ、疫学的な「100ミリシーベルト以下の被ばく領域では放射線影響はみられない」という評価と、「被ばくは少ない方が良い」との放射線防護上の立場から100ミリシーベルト以上における線量と影響の直線関係を、それ以下にも延長して安全面に配慮したと一般公衆に説明しても、納得してもらえないことを示している。
それならば、疫学的研究とは別の視点から低線量被ばく影響を全身から器官、組織、細胞そして遺伝子レベルに至るまで検証し、より明確な科学的証拠を示すことが要請されていると考えるべきではなかろか。そのための科学的、技術的手段を入手できる文明的環境に至っていると思われる。
人類将来の重要なエネルギー源として原子力利用の是非を冷静に議論し、選択判断をするには、上に述べた2課題の戦略的かつ総合的研究が必須であることを福島事故から教えられている。
以上